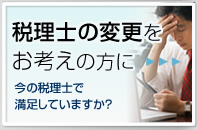居住用財産の特別控除―共有家屋の一部を取り壊してその敷地を譲渡した場合―
(東京高裁平成22年7月15日判決、判時2088号63頁、TAINSコードZ888-1538)
事実の概要
本件は、宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する確定申告をした原告が、当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年改正前)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして、更正の請求をしたところ、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、当該通知処分の取り消しを求めたものである。
- 原告は乙と丙の長女であり、兄の丁、弟の戊の2人の兄弟がいる。
- 乙は平成11年5月11日に死亡。本件土地、及び本件土地に存する本件建物のうち持分1/4を保有。
- 丁は平成13年4月10日死亡。本件建物のうち持分3/4を保有。丁所有本件建物持分は妻の己が相続により取得。
- 平成15年11月1日遺産分割協議成立。乙所有本件建物持分、及び本件土地のうち持分1/4を原告が取得。乙所有本件土地のうち持分3/4を丁(代襲相続により己)が取得
- 平成16年6月29日〜7月4日、本件建物の一部(原告所有部分)を取り壊し。
- 平成16年7月7日、原告、本件建物持分、己への贈与を起因とする所有権移転登記。(贈与日平成16年7月3日)
- 平成18年3月10日、原告、小田原税務署に確定申告。(譲渡所得1,613万円余、所得税額210万円余)
- 平成18年12月27日、原告、小田原税務署に更正の請求。(居住用財産の譲渡所得の特例の適用があるとして譲渡所得ゼロ、税額ゼロ)
- 平成19年4月25日、被告小田原税務署長、本件通知処分。平成19年6月20日、原告、異議申立。平成19年9月19日、被告、異議申立棄却。平成19年10月15日、原告、審査請求。平成20年4月18日、裁決(棄却)。平成20年10月2日、訴訟提起。
当事者の主張
<争点1>本件譲渡に本件特別控除の適用があるか否か
| 原告の主張 | 被告の主張 |
居住用の家屋とその敷地の用に供されている土地を譲渡する方法としては、家屋と土地を一体として売却する方法だけではなく、家屋を取り壊して土地を更地にした上で売却する方法も一般的な不動産取引として行われているが、本件特別控除の趣旨からは、このような場合も、措置法35条1項に定める家屋とともにその敷地を譲渡した場合に該当すると解するべきである。したがって、個人がその居住の用に供している家屋の全部を、その敷地の用に供されている土地を更地として譲渡する目的で取り壊して当該土地を譲渡した場合には、本件特別控除の適用がある。 また、居住用家屋の一部を譲渡した場合であっても、当該譲渡した部分以外が機能的に見て独立した居住用の家屋と認められない場合には、譲渡によって自己の所有する居住用家屋を失ったといえ、当該譲渡についても本件特別控除の適用はあると解されていることからすれば、個人がその居住の用に供している家屋の一部を、その敷地の用に供されている土地を更地として譲渡する目的で取り壊して当該土地を譲渡した場合、取り壊されなかった残部が機能的にみて独立した居住用の家屋と認められないときは、本件特別控除の適用がある。 |
納税者が居住用家屋の一部を取り壊し、その敷地のみを譲渡した場合に、残存する家屋が居住の用に供し得ない場合には本件特別控除を適用することができると解するとしても、本件残存家屋部分には本件共用部分があり、現実にも己が居住していることから、機能的にみて独立した一個の居住用の家屋として存在しているものと認められる。 |
| 原告及び己は、乙の相続財産に係る遺産分割の協議に当たり、本件建物の共有関係及び本件建物における生活関係を解消する方法について協議をし、その結果として、本件建物を2つに分割し、原告が取得する本件建物の分割部分を取り壊し、また、当該土地を2つに分筆し、原告が取得する土地を更地にして第三者に売却し、原告がその売却代金を取得して他に転居するとの合意をした。そして、遅くとも平成16年5月ころまでに、本件家屋部分を取り壊して本件土地を更地として譲渡することを可能とするため、己が本件家屋部分を取り壊すことに同意するとともに、原告が己に本件建物の持分1/4を譲渡する旨を合意をした。そして、この合意に基づいて、同年6月29日から同年7月4日までの間に、本件家屋部分が取り壊され、そのころ、本件建物の持分1/4が己に譲渡されたところ、遅くとも本件家屋部分が取り壊された時点で己が上記合意に基づいて本件残存家屋部分の単独所有権を取得したものと解される。以上のとおり、原告及び己は、その共有物であった本件建物をその持分及び居住実態に応じて分割し、原告が取得した分割部分である本件家屋部分を取り壊して、更地になった本件土地を売却したものである。そして、本件家屋部分は、原告が起居等の日常生活を行い、その生活の拠点として使用していた場所であり、原告の居住の用に供していた家屋に該当する。他方、原告と己は義理の姉妹の関係にすぎず、電気代、ガス代、水道代等の公共料金も使用人数に応じ半額を原告が己に支払うなど生計も別であったことから、社会通念上、原告と同居することが通常であるとは認められず、己の居住の用に供されていた家屋部分は、原告の居住の用に供されている家屋には該当しない。 | 原告は、本件建物を原告の居住部分と己の居住部分とに区分し、その上で、本件譲渡に本件特別控除を適用することができると主張する。しかし、原告及び己は、物理的に区切りのない本件建物を共有してこれに居住し、日常生活を営む上で、重要な意味を有する本件共用部分を共用し、本件建物への水道及び電気の供給に係る契約についてはいずれも己が契約し、電気水道代全額を支払っていた。このような状況からすれば、原告及び己が、本件建物のうち原告の居住部分と己の居住部分とを区分し、それぞれ完全に独立した生活をしていたとはいえないから、原告の上記主張はその前提を欠く。また、原告は、本件建物を原告が専有し起居していた部分とそれ以外の部分に分割し、原告が当該専有する部分を、己がそれ以外の部分をそれぞれ取得したと主張する。しかし、上記原告が取得したとされる部分は区分所有の対象ではなく、1個の独立した物でもないから、独立の所有権の対象とはならず、原告の上記主張はその前提を欠く。本件建物に係る原告の共有部分1/4は本件建物の全体に及んでいるのであり、原告は、本件家屋部分の取り壊し後も本件残存家屋部分の持分1/4を有していた。したがって、本件家屋部分の取り壊しにより原告の居住の用に供している家屋の全部を取り壊したことにはならない。 |
<争点2>原告が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことにつき、「やむを得ない事情」があったといえるか否か
| 原告の主張 | 被告の主張 |
措置法35条1項の趣旨を達成するためには、本来、同項の要件に該当する場合にはすべて本件特別控除を適用すべきであるといえる。しかし、課税庁としては納税者による情報提供がなければ本件特別控除の適用があるか否かを判断することができないし、また、本件特別控除が適用されることを望まない納税者の意思に反してまでその適用を強制することは妥当でない。そこで、措置法35条2項は、確定申告書に本件特別控除の適用を受けようとする旨及び同条1項の要件に該当する旨の事情を記載することを求めるとともに、財務省令で定める書類の添付を求め、同項に該当する事情等の情報を納税者側から提供することを求めている。他方で、措置法35条2項の規定を機械的に適用すると、本件特別控除の適用を望まない者への適用が排除されるのみではなく、本件特別控除の適用を望む者についても確定申告書への記載等がないという理由のみで本件特別控除の適用が排除される結果が生じるおそれがある。そこで、措置法35条3項は、確定申告書への記載等がなかったことについて「やむを得ない事情があるとき」には本件特別控除の適用がある旨を明らかにしたものであり、同項は、その真意から本件特別控除の適用を望まない選択を行った者が更正の請求を行うことを排除するための規定である。したがって、「やむを得ない事情があるとき」に該当する場合は幅広く認められるべきであり、納税者に対して本件特別控除の適用を拒否することが不当又は酷になる場合を広くいうと解するべきである |
措置法35条3項は、同条1項の適用を受けるための手続に厳格な様式行為を備えることを要求する結果として生じ得るであろう不都合を防止する趣旨であるところ、確定申告書に特例を適用する旨を記載し、かつ、必要書類を添付する行為は、納税者の課税上の選択権の行使としての意味を持つものであるから、いったん選択権を行使した納税者について、当該選択の変更を容易に認めた場合には、租税債権の早期安定を阻害することになる。したがって、同条3項に定める「やむを得ない事情」とは、天災その他納税者の責めに帰すことのない事由により、確定申告書を提出すること又は確定申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載すること若しくはそのための資料を添付することが不可能であったと認められるような客観的事情を指すものであり、納税者個人の主観的事情はこれに当たらないと解される。 |
| 本件において、原告は、小田原税務署を4回訪問し、担当官に本件特別控除の適用を望む旨を伝えた上で、それが認められるか否かを相談するという慎重な対応をしたが、いずれの際も、本件特別控除の適用がない旨の回答を受けた。また、原告は、税理士にも本件特別控除の適用について相談したが、本件特別控除の適用を受ける前提で確定申告を行った場合に更正処分を受けることがないとの確信まではないとの回答を受けた。さらに、本件のような事例に係る判例等の先例もない。かかる状況の下で、本件特別控除の適用を受ける前提で確定申告を行えば、後に更正処分を受けることは明らかであり、訴訟において敗訴する危険性もあった。このような場合、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分がされることを承知の上で課税庁の見解に反する申告を納税者に強制することは納税者に酷であるし、いったん課税庁の見解に従った申告をした後に更正の請求を認める方が納税者の事前の納税者の義務の履行を確保することになり、被告の利益につながる。現実に、過少申告加算税を支払う危険を避けるため、いったん課税庁の見解に従った申告を行った後に、更正の請求を行うことは一般に行われている。 | 原告は、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったのは、原告がその適用を受けたい旨を告げて小田原税務署で相談をした際、相談に応対した税務職員が、本件特別控除の適用を受けられない旨指導したことによるものであると主張する。しかし、仮にこのような事実があったとしても、一般に税務相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の一方的な申立てに基づき、その申立ての範囲内で、行政サービスとしての納税申告をする際の参考とするために、税務署の一応の判断を示すものであって、仮に、その相談が課税にかかわる個別具体的なものであったとしても、その助言内容どおりの納税申告をした場合には、その申告内容を是認することまでを意味するものではなく、最終的にいかなる税務申告をすべきかは納税義務者の判断と責任に任されている。したがって、原告が主張するような相談の事実があったということをもって、措置法35条3項に規定する「やむを得ない事情」があったということはできない。 |
| 課税庁の見解に従った申告を行った後に更正の請求がされた場合、自らの見解が正しいのであれば、課税庁としては措置法35条1項の適用がないことを理由に更正すべき理由がない旨の通知処分を行えば足りるはずである。課税庁の見解が誤りであったと課税庁が認識しながら、課税庁の誤った見解に従った納税者に対し、確定申告書上の選択がないことを理由に更正の請求を認めないことは、いわゆる合法性の原則からみても不当であるし、課税庁が納税者に誤った助言をしておきながら、その助言に従ったことを理由に、過大な租税の支払を行った納税者の救済をしないことは、合法性の原則から是認されない。 | 原告が本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかった理由は、本件土地の譲渡について措置法35条1項の適用があるか否かについて税理士等の専門家や税務職員の見解などを聴取した上で十分に検討した結果、過少申告加算税の対象になるのではないかとの懸念を持ったことなどから自ら同項の適用を受けないことを選択したというものであるから、原告の個人的な事情によるものであるし、原告は、所得税について相当な知識があるか、あるいは税について専門的知識を有する税理士等の専門家に相談した上で、本件特別控除の適用を受けようとする旨の確定申告書を提出した上で、本件特別控除の適用を受けようとする旨の確定申告書を提出するか否かの判断をしたものであるから、確定申告書の記載と原告の意思との間に錯誤があったとはいえない。 |
【東京地裁平成21年11月4日判決】
(1)ア 措置法35条1項は、土地又はその土地上に存する権利の譲渡に関しては、災害により当該土地の上に存する家屋が滅失した場合を除いては、個人の居住の用に供し、又は供されていた家屋が現存し、かつ、その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡がされる場合のみを本件特別控除の対象としており、家屋を任意に取り壊すなどした上でその敷地の用に供されていた土地のみの譲渡をする場合については、直接の定めを置いておらず、このような場合については基本的にその適用をすることは想定されていないものと解される。しかし、その上に家屋の存する土地の取引において、当該家屋を必要としない買主が、当該家屋を売主の負担において取り壊すことを求めることがしばしば見られるとの公知の事情や、上記に述べた措置法35条1項の趣旨からすれば、個人が、その居住の用に供している家屋をその敷地の用に供されている土地を更地として譲渡する目的で取り壊した上、当該土地のみの譲渡をした場合は、上記の家屋をその敷地の用に供されている土地とともに譲渡した場合に準ずるものとして、措置法35条1項の要件に該当し得ると解することができる。一方、個人が、その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地の一部を更地として譲渡するために当該家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の部分の譲渡をした場合については、措置法35条1項の文理のほか、建物の所有権その他の権利の対象としての特性に照らし、同項にいう家屋の譲渡が当該家屋の全体の譲渡を意味するものと解されることを勘案すると、当該家屋の全体が取り壊された場合と当然には同列に論じ難いが、この一部の取壊しが当該部分の敷地の用に供されていた土地の部分を更地として譲渡するために必要な限度のものであり、かつ、上記の取壊しによって当該家屋の残存部分がその物理的形状等に照らし居住の用に供し得なくなったということができるときは、当該家屋の全体が取り壊された場合に準ずるものとして、当該譲渡につき措置法35条1項を適用し得ると解される。
そして、上記に述べたところは、取り壊された家屋が共有物であったとの一事をもって、直ちに異なって解すべき根拠は見当たらない。
イ そこで、本件について検討するに、事実によれば、平成16年6月から7月にかけて本件家屋部分が取り壊された後も、本件残存家屋部分の1階には本件共用部分及び居室が残存するとともに、その2階には取壊し前の居室が従前どおり残存し、かつ、己が上記取壊し後も本件残存家屋部分に居住し続けたのであるから、その取壊しにより、本件残存家屋部分が居住の用に供し得なくなったということはできない。
(2)ア 原告は、本件家屋部分を取り壊すことは、原告の居住の用に供していた家屋の全体を、その敷地の用に供されている土地である本件土地を更地として譲渡する目的で取り壊したものといえるから、本件譲渡につき本件特別控除の適用がある旨主張する。
しかし、事実及び証拠によれば、本件建物にあっては、別紙図面に示されているように、本件家屋部分に属しそこに存する2部屋の居室の唯一の出入口となっていた縁側と本件残存家屋部分に属するその2階への階段のいわゆる踊り場とは連続する構造となっており、これらの間を遮断する隔壁等の建物の構成部分は存在しなかったことが認められ、また、既に述べたように、本件建物にあっては、玄関、台所、浴室及びトイレが本件残存家屋部分に属する1階の本件共用部分にそれぞれ各1箇所に設けられているのみであり、平成16年当時、原告は、上記の本件共用部分を己と共用していたものと推認され、本件残存家屋部分にもこれらの設備が残存しているところである。このような本件建物の構造及び利用状況に照らすと、本件建物につき実質的には本件家屋部分と本件残存家屋部分の2棟の建物であったと評価することはできず、また、本件家屋部分につき構造上区分されることにより独立して住居としての用途に供することができるものに当たると評価することもできないことに加え、本件の事実経過の下においては、本件家屋部分の取壊し後も本件残存家屋部分につき原告が持分4分の1を有し、これを己に贈与したと評価されることなども併せ考慮すれば、平成16年6月から7月に行われた本件建物中の本件家屋部分の取壊しをもって、原告がその居住の用に供している家屋全部を取り壊したと評価することはできない。
また、原告は、原告と己との間の共有物分割の合意により、本件建物が本件家屋部分と本件残存家屋部分とに現物分割され、原告が本件家屋部分の所有権を取得してその全体を取り壊し、他方、己が本件残存家屋部分の単独所有権を取得した旨を主張する。
しかし、本件建物の構造等からすれば、原告と己との合意をもって直ちに本件家屋部分と本件残存家屋部分とがそれぞれ別個の所有権の客体になると解することはできない。また、本件建物につき各登記がされており、他方、本件家屋部分が取り壊された時点で己が当然に本件残存家屋部分につき単独で所有権を有することとなるとする合意等がされたことを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告は、本件建物のうち原告が「居住の用に供している部分」といえるのは、本件家屋部分及び本件残存家屋部分に属する本件共用部分のみであったところ、本件家屋部分の取壊しにより、上記のうち本件共用部分のみが残存し、原告との関係では、本件共用部分のみでは、機能的に見て独立して居住の用に供し得なくなったとして、本件譲渡につき本件特別控除の適用がある旨主張する。
しかし、原告の上記の主張は、建物の一部の取壊しの場合について広く本件特別控除の適用があるとするもので、その前提において問題があるというべきである。また、原告は、平成16年当時、己とともに本件建物に居住していたところ、本件建物の構造は別紙図面のとおりであったことに加え、己が原告の義姉であり、原告及び己が乙及び丁の生前から長期間にわたって本件建物に居住していて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、これらの者が死亡するまでの間は本件建物に居住していた親族間の関係は平穏であり、その死亡後も生活状況としては基本的に従前のものを継続するものであったと認められること、現に、本件建物への水道及び電気の供給に係る契約は己名義でされていたことなどを勘案すれば、本件家屋部分及び本件共用部分について、親族間の情宜を基礎とした事実上の区分を超えて、それらの部分のみを原告の居住の用に供することと定められていたと認めることには疑問を差し挟む余地が残るというべきである。
そして、本件においては、本件建物は、その一部取壊し後もいまだその経済的効用を維持しているのであるから、原告が本件残存家屋部分に居住し続けずに転居したとしても、措置法35条1項は適用されないというべきであり、原告の上記主張を採用することはできない。
| 1 2 3 | 次へ |