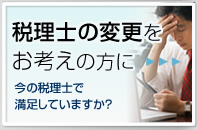一人親方の外注費の課税仕入該当性
事実の概要
本件は、電気工事の設計施工等を業とする原告が、原告の業務に従事した6名に対して支払った金員につき、これらを請負契約に基づいて支出した外注費に当たるとして、同金員を課税仕入に該当し、源泉徴収義務はないものとして平成13年期(平成12年4月1日~平成13年3月31日)、平成14年期(平成13年4月1日~平成14年3月31日)、平成15年期(平成14年4月1日~平成15年3月31日)における確定申告を行ったところ、杉並税務署長は、同金員は、所得税法28条1項に規定する給与等に当り、消費税法上課税仕入に該当せず、源泉徴収義務がある旨の更正処分、納税告知処分、および各加算税の賦課決定処分を受けたため、これらの処分の取消を求める事案である。
前提事実
(1)原告は株式会社Bの専属下請会社であり、原告代表者甲は元使用人兼務役員。
(2)ア 丁、戊、C、D、E、F(6人併せて「本件各支払先」)は、原告との間で1日の労務に係る対価の額を口頭で約束し、原告がBから請け負った業務に従事していた。
イ 本件各支払先は、それぞれが作業に従事する各仕事先において、甲またはB職員である現場代理人の指揮監督の下、作業に従事していた。
ウ 本件各支払先は、各仕事先で使用する材料を原告またはBから無償で支給されていた。
エ 本件各支払先は、各仕事先で作業するに当たり使用する工具及び器具等のうち、ペンチ、ナイフ、ドライバー等は各自で用意していたが、その他各仕事先で使用する作業台、脚立、夜間照明用の発電機及び足場等の工具及び器具等はBから無償で貸与されており、また、各仕事先で着用する作業着は原告から無償で貸与されていた。
なお、上記作業着は、Bがその着用を義務付けているものであるところ、原告は、本件各支払先に無償貸与する作業着をBが指定する業者から購入し、その購入費を福利厚生費として費用計上していた。
オ 本件各支払先は、原告に対して、現場名、出勤日、残業時間及び夜間勤務日等を記載した出勤簿等あるいは、請求書と題する同様の事項を記載した書面を作成し、これらを提出していた。
カ 原告は、本件各支払先から提出された書面に基づき、本件各支払先に対する支払金額として、1日あたりに基本給に各仕事先における従事日数を乗じた金額のほか、1時間あたりの残業給に残業時間を乗じた金額、遅刻言及に係る金額、消費税等の金額及びこれらの金額の合計額等を記載した労務費明細書を作成していた。
キ 原告は、労務費明細書に基づき、本件各支払先へ金員(「本件支出金」)を支払い、①本件支出金を外注費として経理し、給与等の源泉徴収の対象とせず、②本件支出金を課税仕入に係る支払対価の額として消費税等の申告を行った。
なお、本件支出金のうち、丁に対する支払金額には、通勤費が含まれていた。
ク 原告は、本件各支払先を、下請業者内訳書ではなく、協力業者従業員名簿に記載し、Bに提出していた。
ケ 原告は、本件各支払先が受信した定期健康診断の費用を負担していた。
コ 原告は、本件各支払先に対して食事代、慰労会及び忘年会等の費用の一部を負担し、これらの負担額を福利厚生費として経理していた。
争点
本件各課税期間における本件各支払先に対する本件支出金の支払いが所得税法28条1項に規定する給与等に該当するか否か
被告Y税務署長の主張
(1)所得税法上の事業所得と給与所得の区別について、最高裁昭和56年4月24日判決(民集35巻3号672頁)は、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的又は時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」と判示した。
(2)給与所得については、具体的には、次に掲げる事項等を総合考慮して判定すべき。 ア 契約の内容が他人の代替を容認するかどうか イ 仕事の遂行にあたり個々の作業について指揮監督を受けるかどうか ウ まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をすることができるかどうか エ 所得者が材料を提供するかどうか オ 作業用具を供与されているかどうか
(3)本件については、①本件各支払先と原告の契約の内容は、他人の代替を容認しないものであること、②本件各支払先は、仕事の遂行にあたり個々の作業について原告の指揮命令を受けていること、③まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、本件各支払先は原告に対し権利として報酬の請求をすることができること、④本件各支払先は、材料を無償で支給されていること、⑤本件各支払先は、各仕事先で作業するに当たり使用する工具及び器具等のうち、ペンチ、ナイフ及びドライバー等は各自で用意していたものの、作業台、脚立、夜間照明用の発電機及び足場等の大部分の工具及び器具等はBから無償で貸与されており、また、本件各支払先が各仕事先で着用する作業着については、原告がBの指定する業者から購入したものを本件各支払先に無償で貸与していたこと、その他、⑥原告がBに対し、本件各支払先を原告に在籍する者として記載した協力業者従業員名簿を提出していたこと、⑦原告は、本件各支払先に対して食事代、慰労会及び忘年会の費用の一部を負担し、これらの負担額を福利厚生費として経理処理しており、また、本件各支払先が受信した定期健康診断の費用を負担していることなどが認められることからすると、本件支出金は、本件各支払先の給与所得であると認めることができる。
原告Xの主張
(1)原告と各支払先の契約は、本件各課税期間において原告と各支払先の間に雇用関係又はそれに類する関係はない。 本件各支払先は、原告において労働保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱われておらず、丁、戊及びCのほか、Hがいわゆる一人親方として労働者災害補償保険に特別加入しており、また、原告が把握しているだけでも、戊、C及びFは各自の事業所得に係る確定申告をしていた。 本件各課税期間に原告において個人下請業者として稼働していたI、J、H、K、L及びM等に対しては、本件各支払先と同様に出勤簿等に基づく労務明細書によって請負代金が計算され、支払われていたのであって、本件各支払先だけがその収入の事業所得性を否認される理由はない。
(2)被告の主張(2)記載の基準は、最高裁昭和56年判決でも述べられていない独自の基準である。 原告と本件各支払先の間において雇用関係ではなく請負関係が選択された理由は、雇用関係によると各種の控除により手取りの収入額が減少することを嫌った本件各支払先らの希望によるものであって、原告において殊更請負関係を選択する利益はない。
(3)被告が給与所得性の判断要素として指摘する作業に関する指揮監督等の点は、原告を含むBの下請業者が元請業者であるBの綿密な工程監理と予算監理に従って工事しているという現代の大規模建設工事の特殊性に基づくものであって、原告と本件各支払先が請負関係にあることと何ら矛盾するものではない。 本件各支払先に対して食事代、慰労会及び忘年会の費用の一部を負担し、これを福利厚生費として経理処理したことは、原告の経理担当者が経理科目の分類を誤ったものにすぎず、むしろこれらの費用負担のほとんどは接待交際費として通常に経理処理されている。 本件各支払先が受診した定期健康診断の費用の負担や、本件各支払先に対する作業着の無償貸与等は、元請業者であるBの下での施工監督責任の徹底によるものである。
(4)本件処分は、以下の点から、適正手続、租税法律主義及び平等原則に違反する。
①平成15年8月に行われた最初の税務調査時から約9箇月という長期間の遅延の末、何らの行政指導もないまま、処分理由すら明らかにすることなく突如としてされたものであること
②調査担当職員は、原告の役員であるGに係る源泉所得税の計算等に際し、扶養控除等申告書を提出すれば甲欄を適用する旨事前指導しておきながら、給与の支払日までに同申告書の提出がなかったことをもって同指導を覆したこと
③調査担当職員が「外注先との請負契約書又は請求書等が存在すれば外注費として認めてもよい」と指導しておきながら、異議申し立てに係る審理の段階でこれらの請求書等が発見されたにもかかわらず、また、審査請求に係る審理の段階で、原告が求めに応じて本件各支払先以外の個人下請業者に関する証拠を提出したにもかかわらず、これらの資料が全く考量されていないこと
地裁の判断<東京地裁平成19年11月16日判決>
1 業務の遂行ないし労務の提供から生ずる所得が所得税法上の事業所得と給与所得のいずれに該当するかを判断するに当たっては、租税負担の公平を図るため、所得を事業所得、給与所得等に分類し、その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨及び目的に照らし、当該業務ないし労務及び所得の態様等を考慮しなければならず、当該業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性及び有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと区別することが相当であり、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的又は時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない(最高裁昭和56年判決参照)。
2(1)原告代表者は、本件各支払先は、3割程度は原告がBから請け負った工事以外の仕事先で作業に従事していた旨供述するが、これは、Bの下請業者として登録している他の業者がBから請け負った工事について、その業者から原告に対し人手不足や作業遅延等を理由として応援要請があったときに、原告が本件各支払先に連絡して同工事の仕事先で作業に従事してもらうという形態のものであり、他の業者から応援要請がされるのは原告に対してであること、同要請に応じた場合の報酬は、他の業者から原告に対して支払われ、原告がこれを本件各支払先に支払っていることなどの事情が認められること、また、本件各支払先は、調査担当職員に対し、原告以外で仕事をいたことはない旨述べていることなどに照らすと、本件各支払先が原告が請け負った工事以外の仕事先で作業に従事していたとしても、本件各支払先は原告に常用され、専属的に原告の下で電気配線工事等の作業に従事していたものと認めることができる。 本件各支払先が各自に割り当てられた作業を更に下請させたこと、本件各支払先が更に労働者等を使用していたこと、原告における作業のほかに兼業をしていたこと、店舗、事務所又は営業所等を有していたこと、会計帳簿等を作成していたこと、ペンチ、ナイフ及びドライバー等のほかに営業用の資産を有していたこと、いわゆる屋号を有していたことなどの事情が存在していたことをうかがわせる主張立証はない。
(2)原告代表者において各仕事先に係る本件各支払先の要望等を調整するなどしていたことは確かであるとしても、少なくとも原告代表者による現場等の指定に従わなかったために本件各支払先が原告において常用される地位にあったことと相反するような事態は生じていなかったものと認めることができる。 本件各支払先は、仕事を休むときや遅刻をするときには、原告代表者に対し連絡をしており、そのような場合、本件各支払先が自ら代替の作業員等を手配することはなかった。
(3)残業給は、基本給を時間給に換算した金額のおおむね2割5分となっており、夜間の基本給は、通常の基本給の5割増しとなっているなど、労働者の時間外労働及び深夜労働について労働基準法等が定める割増賃金額におおむね準じる額になっている。 本件各支払先は、おおむね週休1日か2日程度で作業に従事していたと認めることができる。 本件各支払先については、1週間で達成すべき仕事量の定めなどがあるものの、それが達成されなかったからといって、労務に対する対価が減少することはない。
(4)原告は、Bとの間で工事請負基本契約書を取り交わしているところ、原告とBとの間の個別の工事に係る契約は、その基本契約に基づき、原告からBに対し見積書を提出し、Bにおいて同見積書を審査した上、原告に対し注文書を発行し、同注文書の交付を受けた原告がBに対して請書を提出することによって成立する。
3(1)本件各支払先は、原告から指定された各仕事先において原告代表者又はBの職員である現場代理人の指示に従い、基本的に午前8時から午後5時までの間、電気配線工事等の作業に従事し、1日当たりの基本給に従事日数を乗じた金額、約2割5分増しの残業給に従事時間を乗じた金額及び5割増しの夜間の基本給に従事日数を乗じた金額の合計額から遅刻による減額分を差し引かれた金員を労務の対価として得ていたこと、この間、原告に常用される者として他の仕事を兼業することがなかったこと、各仕事先で使用する材料を仕入れたことはなかったこと、ペンチ、ナイフ及びドライバー等のほかに本件各支払先において使用する工具及び器具等その他営業用の資産を所持したことはなかったことなどが認められるところ、さらに、原告が本件各支払先に係る定期健康診断の費用を負担していたこと、原告が福利厚生費として計上した費用をもって本件各支払先に無償貸与する作業着を購入していたことなどを総合的に考慮すると、その労務の実態は、いわゆる日給月給で雇用される労働者と変わりがないものと認めることができるから、このような本件各支払先について、自己の計算と危険において独立して電気配線工事業等を営んでいたものと認めることはできない。
(2)そもそも課税要件事実は、表面的に存在するように見える法律関係に即してではなく、真実に存在する法律関係に即して認定をするべきであるところ、その認定に当たり、私法上の契約関係に係る当事者の意思ないし認識を考慮に入れることは当然ではあるが、本件では、たとえ原告と本件各支払先の間でその労務が請負契約に基づくものであるとして取り扱う旨の認識があったとしても、本件各支払先としては、原告に対し、ある仕事を完成することを約して労務に従事していたと認めることはできず、労働に従事することを約して労務に従事する意思があったものと認めるのが相当であり、実際、原告と本件各支払先の契約関係では、他人の代替による労務の提供を容認しているとはできないこと、本件各支払先は原告代表者又はBの職員である現場代理人の指揮命令に服して労務を提供していたことが認められることなどからすると、本件各支払先による労務の提供及びこれに対する原告による報酬の支払は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、原告との関係において空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に労務の提供を受けていたことの対価として支給されていたものと認めるのが相当である。
(3)したがって、所得を事業所得、給与所得等に分類し、その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨及び目的や、他の給与所得者等との租税負担の公平の観点等に照らし、本件各課税期間における本件各支払先に対する本件支出金の支払は、所得税法28条1項に規定する給与等に該当するものと認めることができる。 そして、このことは、原告がBに対し、本件各支払先を原告に在籍する従業員として記載した協力業者従業員名簿を提出していることからも裏付けることができ、また、原告において本件各支払先に対して食事代、慰労会及び忘年会等の費用の一部を負担し、これらの負担額を福利厚生費として経理していたことからも裏付けることができる。
4 原告と本件各支払先とは、原告が資本の額を1000万円とする株式会社であることに比べ、本件各支払先はペンチ、ナイフ及びドライバー等以外の営業用資産を所持していないという違いがあるほか、Bと原告及び原告と本件各支払先との関係は、工事請負基本契約書の作成の有無を始めとして様々な違いがあるのであって、原告及び本件各支払先が共にBの指定する詳細な作業指示に従わざるを得ないことなどをもって、原告がBとの関係で下請業者であることと同様に本件各支払先が原告との関係で請負契約に基づく事業所得者であると認めなければ不相当であるとはいえない。 上記①については、本件各処分について理由を付記すべきことを求める法令上の根拠はなく、本件各処分に先立って事業所得と給与所得の区分等について何らかの行政指導をしなかったものとしても、それが直ちに適正手続に違反するとまではいえない。 上記②については、本件全証拠によるも、処分行政庁の行為が信義則に違反するといえる事情を認めることはできない(最高裁昭和62年10月30日判決参照)。 上記③は、異議決定及び審査裁決の違法又は不当を主張するものであって、本件各処分の違法を主張するものではなく、失当である。
高裁の判断<東京高裁平成20年4月23日判決>
地裁判決に下記の点を追加するのみ
1(2)控訴人は、上記(1)の「租税負担の公平」の内実は、事業所得として本件支払先に確定申告させるよりは、給与所得として控訴人から源泉徴収する方が課税しやすいという税務当局側の結論先行の価値判断を理由なく追認するものである旨主張するが、所得税法は、事業所得と給与所得とではそれぞれの所得の金額につき異なる扱いをしているのであって、各種所得の種類に応じた課税をすることは、課税の公平を維持する上で不可欠であり、上記(1)の判断の枠組みは、所論のような課税の便宜等の観点から一義的に所論の結論を導こうとするものでないことは明らかであって、上記主張は失当である。
3(2’)控訴人は、(ア)私人間に真実に存在する法律関係は、私法上の契約関係に係る当事者の意思ないし認識、税務申告上の認識、租税回避の意思の有無等と関係なく又はそれに反して成り立ち得るものではなく、当事者の意思の合致により選択された契約の結果が当事者以外の外部的機関の認定により覆されると、国民の経済活動に支障が生ずるし、(イ)仮に本件支払先が所得税源泉控除や社会保険料控除まで真実に認識していたとすれば、私法上、控訴人との法律関係につき請負契約を選択して自ら税務申告をすることはあり得ず、本件における真実に存在する法律関係が請負契約であることは証拠上も明白である旨主張する。
しかしながら、①控訴人と本件支払先との間の法律関係が雇用ないし請負のいずれに該当するかは、当該事案における当該業務ないし労務及び所得等の態様などの客観的な事実関係に即した法的評価に係る事柄であり、このような客観的な評価と控訴人の主観的な意図との間に認識・見解の相違が存在するとしても、それによって当該法律関係の客観的な評価が左右されるものではなく、その客観的な評価に従って税務行政が遂行されることを論難する所論は当を得ておらず、②本件においても、上記のとおり、当該業務ないし労務及び所得等の客観的な事実関係を総合的に考慮すれば、控訴人と本件支払先との間に真実に存在する法律関係は、客観的な評価としては、雇用契約又はこれに類する原因と認めるのが相当であり、本件の全証拠によっても、これを請負契約と評価し得る事実関係の存在を認めるに足りないというべきである。
4(1)控訴人は、(ア)控訴人において稼働していた下請業者は、個人・法人ともに、従前から一貫して出勤簿等に基づく労務費明細書によって請負代金が計算されて支払われていたことから、その計算方法は「人工数×残業時間」によらざるを得ないことは明らかであり、請負代金の定額性等の事情は請負契約性と矛盾するものではない、(イ)控訴人においては、役員及び従業員のみが社会保険及び雇用保険の被保険者であり、本件各支払先を含む下請業者は、社会保険及び雇用保険の被保険者として取り扱われておらず、一人親方として労働者災害補償保険に加入していた旨主張し、これらの点からも、常用の有無を認定基準として本件各支払先につき請負契約性を否定することは不当かつ誤りである旨主張する。 しかしながら、本件各支払先への支払は、各人が控訴人に常用されて専属的かつ継続的に控訴人の下で稼働する状況の下で、基本給並びに労働基準法等が定める時間外労働・深夜労働に係る割増賃金額におおむね準ずる残業給及び夜間の基本給によって、継続的に行われていたこと、控訴人は、本件各支払先の定期健康診断の費用を負担し、福利厚生費として計上した費用で本件各支払先に無償貸与する作業着を購入していたこと等に照らすと、上記主張を考慮しても、前記認定が左右されるものではない。
考察
1.民法上の雇用契約と請負契約
およそ他人の労力を利用する契約(労務供給契約)には4つの種類がある。?は、他人の労務自体の利用を目的とするもので、労務者を指図して、一定の目的に向けて効果を発揮させる権能は使用者に属する。雇用がこれである。2は、他人の労力によって一定の仕事の完成を目的とするもので、労務者がみずからその労務を按配しその危険において仕事の完成に努めるのである。請負がこれに属する。3は、一定の事務の処理という統一した労務を目的とするもので、必ずしも完成した事務の結果のみを目的とはしないが、事務の処理は労務者が独自の識見才能によってこれをするのである。委任がこれに属する。4は、他人の物を保管するという特殊の労務を目的とする。寄託がこれに属する。右のうち先の三者は場合によっては区別が困難なことも少なくない。たとえば、いわゆる「出来高払の賃金」を支払うとき、特に仕事の場所が労務者の自宅である場合は、雇用であるか請負であるかが不明となる。(我妻栄・有泉亨(水本浩補訂)『民法2[第4版]』一粒社平成4年316頁)
民法の雇用契約は、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する」契約とされている(623条)。この雇用契約と労働契約との関係については、範囲が一致する概念であるという見解と範囲が異なるという見解が対立してきた。しかし、労働契約に該当するか否かについては、労働関係の実態に即して判断されるべきものであって、契約の形式が「請負」ないし「委任」であっても、契約関係の実態において[使用されて労働し、賃金が支払われる]関係と認められれば「労働契約」に該当しうる、というのが、学説・裁判例においてほぼ一致した見解である。そして、「雇用契約」に該当するか否かについても、同様に契約の形式が「請負」ないし「委任」であっても、契約関係の実態において[労働に従事し、報酬を受ける]関係と認められれば「雇用関係」に該当するというべきであろう。そうとすれば、「労働契約」と「雇用契約」も基本的に同一の概念とみることができる。(菅野和夫『労働法[第8版]』弘文堂平成20年68頁)
請負の目的は、仕事の完成です。そのため、請負は、一面では売買的要素がありますが、他方では、請負は仕事の完成に関する限り、労務をその対象としています。したがって、請負は雇用や委任と同じように他人の労務を利用する「労働供給契約」の一類型になります。しかし、請負は雇用のように労務そのものの供給を目的とするものではなく、また、注文者の指揮命令を受けません。 雇用では、労働が従属性を持つのに対して、請負には労働の独立性があり、仕事の完成を目的として労働が行われます。したがって、雇用の場合は、労働力を提供さえすれば労働の成果に関係なく報酬がもらえますが、請負では仕事が完成しないともらえません。このため、請負では、仕事完成後、引渡しまでの間に当事者の責に帰すべからざる事由によって目的物が滅失毀損した場合、仕事が完成可能である限り完成義務はなくならないと解されます。また、仕事の完成が不可能であれば、危険負担の原則(民536①)により、報酬請求権がないことになります。(山口康夫『判例にみる請負契約の法律関係』新日本法規平成18年13頁)
業務委託、または業務請負という用語は、実務における通称で、法律の規定した概念ではありません。実務での契約書には、「業務委託契約」「業務請負契約」「業務委託請負契約」「委託契約」「請負契約」等、さまざまな表題が付けられており、用語の使用については統一されていない状態です。 一般に業務委託とは、個人が委託者から委託を受けて、労働契約以外の労務供給契約に基づいて、委託者の協力の下に委託された業務を行い、報酬を得ることをいいます。このために当事者の間で結ばれる契約が、業務委託契約です。業務委託によって労働を供給する者は、「委託労働者」と呼ばれます。 業務請負は、発注者と業務請負企業が、業務請負契約を結び、その契約上の債務を履行するために発注者の協力の下に自己の雇用する労働者、または委託労働者を業務に従事させ、報酬を得ることをいいます。ここに従事する労働者は「請負労働者」と呼ばれます。 業務委託、業務請負は、委託者、発注者が、委託労働者、業務請負企業に対し、業務遂行に必要な情報・機械・設備等を提供し、業務内容等に指示を与え、これに委託労働者や業務委託企業が常時指示、監督を受けるという関係にあります。当事者の間で業務内容、報酬額、契約期間等の契約条件を契約期間中に任意に変更することも予定されています。 (山口、前掲書、410頁)
委託労働者は、その多くは特定の委託者に仕事の受注を依存していますから、委託者の提示する契約条件を受け入れる傾向があります。これは、特に報酬単価の低さとなって現れます。また、契約書が作成されない例も多く、労務供給の条件が不安定、不明確になっています。その一方では、委託労働者は、自営型を基礎としていますので、労働法の適用がないものとされ、労働保険・社会保険も未加入であり、業務災害の場合も委託労働者自身の負担となります。(山口、前掲書、411頁)
委託労働者が労働基準法上の「労働者」に該当するのかどうかは、これまでしばしば争われてきました。労働基準法は、労働者に関して「使用される者で、賃金を支払われる者」(労基9)としています。しかし、この規定は抽象的であるために、具体的内容が問題となってきました。
最高裁平成8年11月28日判決(判時1589号136頁)は、車の持込運転手の労働者性に関する、最初の最高裁判決ですが、同判決は、労働者性について「使用従属性」を基準に判断しています。
使用従属性は、「労働基準法研究会報告書」(1985年)において「労働基準法の『労働者』の判断基準」で示された基準ですが、これによれば、労働者性は契約形式によるのではなく、実質的な使用従属性の関係があるかどうかにより判断すべきであると指摘されています。そして、使用従属性の基準として、指揮監督関係、報酬の労務対価性が挙げられ、具体的には、①仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③勤務場所・時間の拘束性の有無、④労務提供の代替性の有無等が判断要素とされています。また、機械・器具の負担関係、労働保険・社会保険加入の有無、退職金制度等が補強的な判断要素とされています。(山口、前掲書、412頁)
2.給与所得と事業所得の所得区分を巡る先行判例
①最高裁昭和53年8月29日判決(月報24巻11号2430頁)<給与所得>
給与所得は、雇用またはこれに類する原因にもとづき非独立的に提供される対価として受ける報酬および実質的にこれに準ずべき給付を意味するものであって、報酬と対価関係に立つ労務の提供が、自己の危険と計算とによらず他人の指揮命令に服してなされる点に、事業所得との本質的な差異がある。したがって、提供される労務の内容自体が事業経営者のそれと異ならず、かつ、精神的、独創的なもの、あるいは特殊高度な技能を要するもので、労務内容につき本人にある程度自主性が認められる場合であっても、その労務が雇用契約等にもとづき他人の指揮命令の下に提供され、その対価として得られた報酬もしくはこれに準ずるものであるかぎり、給与所得に該当するといわなければならない。・・・ Xがバイオリニストとして高度の技術を有し、かつ、日フィルからうける報酬が、X主張の如く、雇傭、請負、委任などの要素の混合した楽団参加契約ともいうべき一種の無名契約に基づくものであるとしても、それはXが楽団に所属し、そのスケジュールに従ってその指揮拘束を受ける従属的立場において提供する役務の報酬として支払われたものであり、Xが右楽団を主宰するものでないことはもちろん、そのスケジュールの企画、策定、実行にも直接参画するものでないことは弁論の全趣旨から明らかであるから、右楽団の一員としてXが活動することは自己の危険と計算による企業性を有するとはいいえないことはもちろんであって、ひっきょうXが日フィルから取得する収入についてYにおいてこれを給与所得と目して課税したことには何ら違法の点はない。
②最高裁昭和56年4月24日判決(民集35巻3号672頁)<事業所得>
およそ業務の遂行ないし労務の提供から生ずる所得が所得税法上の事業所得と給与所得のいずれかに該当するかの判断するにあたっては、租税負担の公平を図るため、所得を事業所得、給与所得等に分類し、その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨、目的に照らし、当該業務ないし労務及び所得の態様等を考察しなければならない。したがって、弁護士の顧問料についても、これを一般的抽象的に事業所得又は給与所得のいずれかに分類すべきものではなく、その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者を次のように区分するのが相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については。とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。・・・
Xは第一東京弁護士会所属の弁護士であり、昭和42年ないし同44年当時、自己の法律事務所を有し、使用人を4人ないし6人を使用して、特定の事件処理のみならず、法律相談、鑑定等の業務もその内容として、継続的に弁護士の業務を営んでおり、各会社とXとの間の本件各顧問契約はいずれも口頭によってなされ、この契約においてXは右各会社の法律相談等に応じて法律家としての意見をのべる業務をなすことが義務づけられているが、この業務は本体の弁護士の業務と別異のものではない。右各顧問契約には勤務時間、勤務場所についての定めがなく、この契約はそのころ常時数社との間で締結されており、特定の会社の業務に定時専従する等格別の拘束を受けるものではなく、この契約の実施状況は、前記各社において多くの場合電話により、時には右各社の担当者がXの事務所を訪れて随時法律問題等につき意見を求め、Xにおいてその都度その事務所において多くは電話により、時には同事務所を訪れた右担当者に対し専ら口頭で右の法律相談等に応じて意見を述べるというものであって、Xの方から右各社に出向くことは全くなく、右の相談回数は会社によって異なり、月に2,3回というところや半年に1回、1年に1回というところもある。右各社はいずれも本件顧問料を弁護士の業務に関する報酬にあたるものとして毎月定時に定額をその10%の所得税を源泉徴収したうえXに支払っており、右顧問料から、健康保険法、厚生年金保健法等による保険料を源泉控除しておらず、Xに対し、夏期手当、年末手当、賞与の類のものを一切支給しておらず、したがって、雇傭契約を前提とする給与として扱っていない。右の事実関係のもとにおいては、本件顧問契約に基づきXが行う業務の態様は、Xが自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎないというべきであり、前記の判断基準に照らせば右業務に基づいて生じた本件顧問料収入は、所得税法上、給与所得ではなく事業所得にあたると認めるのが相当である。
③福岡高裁昭和63年11月22日判決(税資166号)<事業所得>
委託検針員の場合、(1)採用過程に一般従業員のそれに類似する面があり、且つ、Xらのように10数年以上検針員を継続しているものがいること、(2)業務内容が九電の直接的な指揮下に行われ、九電から身分証明書が交付されたり、社名入り作業衣等が貸与されたりしていること、(3)定例日制のため、検針日が定まっていて、裁量の余地がないこと、(4)委託業務中に本来の検針業務のほか付帯業務が含まれていること、(5)月に1回程度打合せ会への出席が求められていること、(6)Xらのように受持枚数の多い者の就業態様、就業時間等が一般従業員のそれに類似していること、(7)同じく受持枚数の多い者の場合、委託手数料も毎月それ程変らぬ金額であって、一般従業員の給与に相応し、また、委託検針員にも毎年夏冬の2回従業員のボーナスに類する特別謝礼金、契約終了時に退職金に類する解約謝礼金が支払われていること等、九電との関係が実質雇用契約に類似する面を有することは否定されない。
しかし、右(1)の採用過程についていえば、委託検針契約は、九電と各委託検針員との間で、具体的な検針地区と定例検針日、検針枚数等を明示した契約書により個別に締結され、且つ、その検針地区、定例検針日、受持枚数も多種多様のものであって、対等当事者間の委任ないし請負契約として効力を有する、といわなければならず、(2)の業務関係も、委託検針員らは、契約で定められた事項によってのみ九電に従属しており、労務の提供につき一般的な指揮命令下にあるわけではなく、(2)の身分証明書、社名入り作業衣、及び(5)の定例打合せ会等は、検針作業の円滑な実施のためのもの、(2)の作業衣等の貸与、(7)の特別謝礼金、解約謝礼金、その他も、委託検針員に対する処遇の改善として逐次実現されてきたものであって、委託検針契約が右委任ないし請負契約であることと必ずしも矛盾するものではない。
特に、(7)の委託手数料は、・・・純粋な形の出来高制であって、労務提供の対価よりも委任ないし請負事務の報酬としての性格を持つというべきであり、(6)の就業態様の関係で、委託検針員に勤務時間の定めがなく、就業時間が定例検針日の日数と受持枚数の如何で異なる点、委託検針員に就業規則による九電の服務規律の拘束がなく、懲戒等もない点、(8)の業務に必要な器具、資材のうち、主要な交通手段であるバイクの購入、維持費等が委託検針員の個人負担である点、(9)検針業務を第三者の代行させることが禁止されてなく、現実に行われている点等は、むしろ雇用契約にはない面といわねばならず、(10)の兼業が自由で実際兼業者が多い点も、一般的には委託検針契約が雇用契約でない方向を裏付けるものである。
④平成13年10月31日裁決<未搭載、関裁(所)平13-24>(事業所得)
A社は、従事日数等に応じて、請求人に対して対価を支払っていることに加え、溶接の際に使用する消耗品をA社が負担していることからみると、給与所得といえなくもないが、①請求人自身が、A社の従業員になることを拒否したこと、②A社は請求人を外注先と認識し、支払を外注費として経理していること、③請求人自身が「製作代」の請求書を作成し、受領した対価についての領収書も発行していること、④A社では、従業員に対する給与の支払いに際しては所得税の源泉徴収を行っているものの、請求人に対する支払に際してはこれを行っていないこと、⑤請求人はA社以外と取引することもできること、⑥請求人は確定申告において、自らの所得を営業所得として申告していることなどの事実を考え併せると、請求人とA社との間には、雇用契約はもちろん雇用関係があるとはいえない上に、請求人が、A社に対して非独立的、従属的な労務の提供をしていたとは認めることができない。
なお、本件書類の「給与支払明細書」である旨の記載は、外注費支払明細書と記載すべきものを誤って記載したものと認めるのが相当であり、また、A社は従業員及び外注先の区別なく、支払に際して「給与支払明細書」を同封していることが認められるから、本件書類をもって請求人の収入金額を給与所得の収入金額とすることはできない。
3.土木作業員への外注費の課税仕入該当性
①岡山地裁平成21年4月14日判決(税資259号65頁)<給与所得>
本件支出金は、定額の日当に就労日数を乗じて計算され、1日8時間の就労時間を超えた場合、時間外手当が加算されて支払われるというのであるから、これは時間賃金そのものにおいてほかならないというべきであって、現に、原告と本件各作業員との間において、本件各作業員が完成すべき仕事が特定され、それにつき納期が定められ、完工検査、納品がされ、仕事の完成ないしその結果に対する対価として代金算定がされている事実を認めるべき証拠はまったく存しない。また、上記事実によれば、安価な個人用軽装品を除き、機械器具や工事用資材はすべて前期元請各社や原告が提供しているというのであるから、本件各作業員は、自ら請け負った仕事の完成のために労働しているとはいい難く、あくまで原告において、機械器具や資材を提供した上、原告が請け負った工事の完成のために労働しているものというべきである。
そして、…本件各作業員は、当日就労するか否かを含めて自由に仕事や場所を選べ、また、本件支出金につき公租公課の徴収、控除を受けないことから、そのような就労形態を希望し、原告もその希望を受け入れていることがうかがわれるところ、これに加えて、本件支出金が日当に就労日数を乗じて計算されることその他上記の諸事情を併せ考慮すると、本件各作業員は、労働基準法21条1項にいう「日々雇い入れられる者」(以下「日々雇用労働者」という)であると認めることができる。
以上のとおりであり、本件支出金は、日々雇用労働者である本件各作業員に対する時間賃金たる性質を有しており、所得税法28条1項の「給与等」に該当するというべきである。
原告は、本件各作業員が一人親方であり、そうであれば、当然、事業者であるから、本件支出金が所得税法28条1項の「給与等」でないことを前提とする主張をするが、本件各作業員の実態は、上記のとおり、日々雇用労働者というべきであり、このような労働者の存在をまったく考慮していない点で不当であるから、上記主張を採用することはできない。
| レポート・刊行物 目次へ |